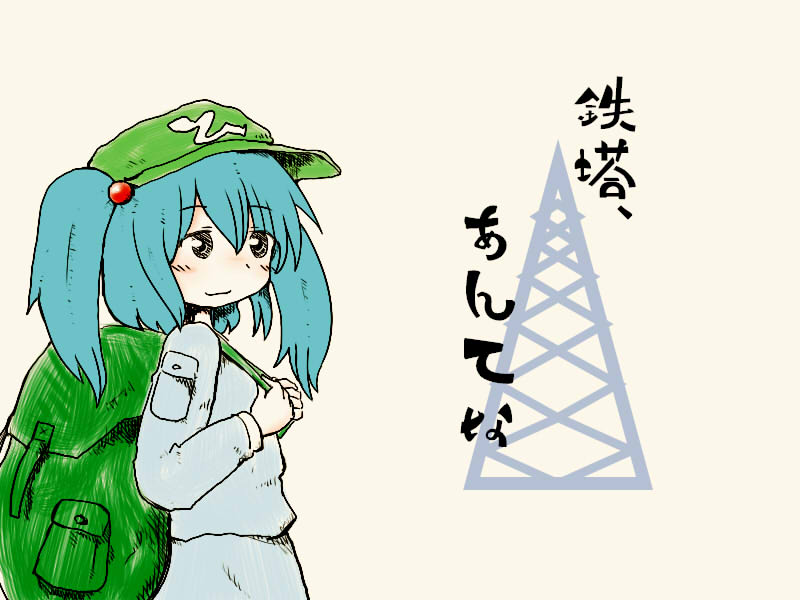
その鉄塔がいつから立っていたのか、正確な事が分かる者は誰も居なかった。
それは背が高く、送電線であったのだろう、中途から腕を広げるように両側に伸び、先端には電線だったであろう太いゴムの紐が風に揺れていた。
妖怪の山の中腹にそびえ立ったそれは、黒い鉄骨のあちこちに赤錆が目立ち、一種異様な雰囲気に包まれていたが、幻想郷の住人は面白がってぞろぞろ集まって来たが、死んだように黙ったまま佇んでいる鉄塔にはすぐに興味をなくし、そうこうしているうちに新しい異変騒ぎが起こり、鉄塔はその存在感にも関わらず、すっかり忘れられたようであった。
しかし、鉄塔は誰に相手にされなくとも、何の変りもなかった。
何かの拍子に錆がはがれた所は鈍く朝日を反射し、夕暮れになれば影を長く伸ばして、近くを通る者にそっとその存在を知らせた。荒い網目状の影にふと顔を上げた者たちは、鉄塔の大きさに圧倒された。そうして、そのどこか荒涼とした美しさにしばし見惚れるのであった。
河城にとりは河童である。
河童は川に住み、機械をいじり、胡瓜を好んで食った。また、新しいものにも目がなかった。
そんな河童たちは、鉄塔が出現した頃には喜び勇んで鉄塔に押しかけ、あれこれと調査をしたが、鉄塔そのものは単に錆にまみれた鉄の塊であり、取り立てて珍しいものではなかった。ただ、その大きさと造形の奇妙さに幾ばくかの興味を引かれたばかりである。
であるからして、河童たちの興味は他の者たちと同様にすぐさま別のものに移って行ったのだが、にとりだけは妙なとっかかりを感じたらしい、他の河童や妖怪たちが姿を消してからも、一人鉄塔の上で物思いに耽った。
鉄塔の背は高く――といっても彼女たち妖怪はもっと高く飛べるのだが、ともかく高い所、そして眺めの良い所で腰を落ち着けられるというのは、にとりには心地よかった。びょうびょう吹く強い風に髪の毛を揺らしていると、煮詰まっていた機械の改造や、設計図の数字や図形から解放されるような気分になったものだ。
にとりの根城に遊びに来ていた一匹の河童は、それを聞いて首を傾げた。
「そんな事をして、何が楽しいのだか分かんないよ」
「別に楽しいからやっているわけじゃないよ」
「じゃあ一体なんなのさ」
「たまには頭を休めてぼんやりする時間が必要なのさ。ただでさえ最近は『外』からの流入品が多いんだし、楽しみはそっちですればいいし」
「やだね年寄り臭くて。そんな事していると、そのうち自分が河童だって事も忘れちゃうよ」
「余計なお世話」
にとりはあっかんべえと舌を出した。
事実、退屈の為に思索と哲学に耽り、自己の存在を曖昧にしてしまった妖怪は古今枚挙するに暇がない。妖怪は実在と観念の間の揺らぎに位置する為、他者からの存在の承認と同じくらい、自己の肯定は大切なのであった。自らの存在に疑問を持つことは、妖怪にとっては緩やかな自殺と同義なのである。
しかし、にとりはそういった思索をしているわけではない。ただ風に吹かれながら風景を眺め、ぼんやりしているだけである。頭の中は空っぽになっているのだが、それが他の河童たちにはムツカシイ考え事に耽っているようで、危なげに見えたのであろう。
ともあれ、そんな事は意に介さず、にとりは日課のように鉄塔に通った。
初めのうち、鉄塔から眺める風景はにとりにはひどく新鮮に映った。ふよふよ浮く事は出来ても、そのまま宙空にとどまって眼下を睥睨するなぞ思いもよらなかったが、こうして足場のある高い所からは、ある落着きを以て辺りを見る事が出来た。
ある時は遠くの山々が、遠くのものになるにつれて、薄青いヴェールをかぶったように濃淡のグラデーションとなって連なっているのを見たし、ある時はあぜ道が彼岸花に覆われていて、その為に田園地帯の金色の稲穂が、紅いラインで四角く区画されているようになっているのも見た。
また、ある夜に鉄塔を下から見上げた時には、その尖端に上手い具合に月が刺さっているようになっているのも見た。月明かりが強く、目を閉じても瞼の裏に光の残滓がうごめくようであった。
にとりはそんなものを見る度に、幻想郷は随分綺麗だったのだと柄にもなく感じ入った。
しかし、基本的に飽きやすい性質であるにとりは、次第に他のものに気を取られ、鉄塔の事を忘れた。その頃には鉄塔もすっかり風景に馴染んでしまっていたので、取り立てて思い出す事もなかったのである。
○
ラジオは初め香霖堂にあった。
例によって店主が無縁塚で拾得し持ち帰ったが、幻想郷に放送局はないので、いくらダイアルを合わせても、地鳴りのような低い音か、さもなくば嵐の中で布を引き裂くような音が聞こえるばかりであった。
にとりは、この妙なガラクタばかり積み上げている店を懇意にしていた。お愛想の欠片もない店主の事は嫌いだったが、見た事のない機械たちはにとりの想像力を刺激し、興奮させた。
一時期は大型機械に凝っていたにとりであったが、ここの所は小型機械に興味が移っていた。手元で小さな部品をちまちまいじくるのが妙に面白かった。
その点に於いて、ラジオはにとりの興味を引くに充分であった。手に取って色々のスイッチを押したり、ダイアルを細かく合わせたりしてみても、ただ不愉快なざあざあ音を撒くだけなのも、返ってにとりの意地に火を点けた。
「へえ、これ壊れてるのかな?」
「さあ、どうかな。用途は電波放送の受信だそうだが、何だかよく分からないからね。何か条件が整わなくちゃいけないのかも知れない」
「ふぅん、まあいいや。はい二十銭」
「なんだ、結局買うのかい」
「分解して調べてみるよ。この変な音の正体も知りたいし」
「案外、故障じゃなくて地底の溶岩や嵐の中に繋がっているのかも知れないな。そういった一種の暴力的なエネルギーを受信する装置だとすると、もしかして災害の対策なんかに使われていた可能性があるんじゃないだろうか」
店主は持論を展開しだしたが、にとりはとうに愛想を尽かして居なくなっていた。
それからしばらくの間、にとりはラジオとにらめっこしながら暮らした。
めっぽう細かくダイアルを合わせてみたり、アンテナを伸ばしたり引っ込めたり、一度バラバラに分解してから、元の通りに組み立ててみたりもした。しかしラジオは一向にざあざあ喚くばかりであった。
幾日もそんな事をして、いい加減にくたびれたので、にとりはラジオを持ったまま散歩に出た。スイッチは入れたままにした。何かの拍子に違う音が聞こえては来ないかと思っての事であった。
沢を下り、川沿いをてっくらもっくら歩いて行くと、次第に秋が深まっているらしい、川の両側で見下ろすように切り立った崖の上で、紅葉しかかった木々が、風に葉をざわめかしていた。同じざあざあいう音でも、こっちの方がよほど風情があるなあ、とにとりは思った。
知り合いの河童と談笑し、将棋仲間の白狼天狗とお茶を飲んだら日が暮れかけた。
友人たちはにとりのぶら下げたラジオの雑音に顔をしかめたが、特に何か言うわけではなかった。友情の成せる業ではなく、単に得体の知れないラジオに言及するのが面倒だっただけである。
にとりとしても、変に文句を言われたり問い詰められたりするのは本意ではなかったし、それで喧嘩に発展しても面白くなかったので、ラジオは喚き立ててはいたが、ちっとも話題には上らなかった。
そうやって気分転換をして、家路をぽくぽくとと歩いていると、不意にラジオのざあざあ音に混じって、人の声が聞こえた。
「んん?」
声は直ぐに消えたが、確かににとりはそれを聞いた。おかしいなと思いながら、ラジオを捧げ持つようにして、あちこちの方角に向けてみると、ある方角に向けた時だけ、その声が聞こえるのを発見した。
「わ、わ、やった。こっちか」
にとりはラジオの音を頼りに、もっと鮮明に聞こえる方を目指して歩いた。ずっと歩いて行くと、ついには雑音は混じらず、すっかり人の声と音楽ばかりが聞こえる場所に辿り着いた。
長い影が頭上からかぶさっている。にとりがハッとして見上げると、あの古びた大きな鉄塔が自分を見下ろしているのに気付いた。
「へえ」
にとりは予想外に鉄塔とラジオがつながった事に、妙な感慨を覚えた。ラジオは流暢に喋っている。
『――十二時になりました久々に明るい話題の朝のニュースの時間です。株式相場は太平洋上に発生した新宿の強盗殺人事件の犯人が西多摩の小学校の稲刈りのイベントに中国で行われた首脳会談で卓球の森永選手が三対一でヤクルトを破りワールドカップ決勝のチケットを手にしました。では現場から中継です』
まるで要領を得ない放送であったが、この小さな機械からたくさんの音が聞こえてくるのが面白くて、にとりは夢中になって耳を傾けた。
聞きながら色々の事を思う。
どうやってこの音は出ているのか、何かの通信機械か、録音か、どうやればここの技術で再現できるか。音と理論と創造と設計図とが頭の中でくるくる回った。
暮れかけていた太陽はすっかり沈み、辺りは暗くなった。遠くの山の稜線に沿って、わずかに残光が揺らめいている。
にとりは鉄塔に上って腰を下ろし、足をぶらぶらさせながらラジオを聞いた。ふと思いついてダイアルを回してみると、一時のざあずずという音の後に、違う声や音が聞こえ出した。外界のものもあるようであったが、何か聞き覚えのある声もした。
『――コラ魔理沙、わたしの布団で勝手に寝るんじゃない!――固い事言うなよぉ、老けるぞ霊夢――ああん? もっぺん言ってみろコラ――うわ、何をするやめ――』
『――退屈だわ、うどんげ、ちょっと首取れなさいよ――嫌です! あっ、やめて師匠、あっ……――……そんなに面白くないわね――どうしてくれるんですか、この頭!――』
「咲夜、紅茶は?――申し訳ありません切らしてまして、代わりにマテ茶を淹れましたから――……何それ?」
『――藍、尻尾をもふもふさせなさい――またですか紫さま、ここの所ずっとですよ――拒否権はないわよ、そーれ、もふもふぅ♪――もー……――』
にとりは何ともいえない気分になりつつも、ダイアルをあちこちに合わした。すると一際やかましい声が聞こえて来た。
『――――東風谷早苗のオールナイト・ニッポ~ン! さあ、やってきました幻想郷でも一番人気のこの番組、今夜もたくさんのお便りをいただいてますよ~。まずはペンネームかにゃっこさんからのお便りで~す。えー、なになに? 最近、相方のノリが悪くて困っています。近々宴会が開かれるのですが、このままでは一発芸に間に合うか不安です……芸人の方ですかねえ、ふふふっ、え~と、きっとそれは戸棚に仕舞ってあったおまんじゅうを食べちゃったからじゃないですかね! 相方さんはきっとかにゃっこさんが食べてしまったと思っていますよ。でお大丈夫、犯人は別にいるはずです! だからきっと仲直り出来……あ、あれ? 神奈子さまいつからそこに? あっ、諏訪子さままで! 部屋に入る時はノックして下さいって何度も……いやあのこれは単なる趣味で録音しているだけであって、決して事実をそのまま話しているわけじゃ……違います、おまんじゅうなんて食べてません! ……え? 違いますよ、こしあんでした。はっ、いや違うんですこれは、あっ、やめてください、うぁ、そこはだめぇ、やっ、あ……――』
にとりが怪訝な顔をしてダイアルを回すと、そこは何も受信しない所らしい、再びざあざあ音が鳴り出した。にとりは嘆息して脱力した。どうやら幻想郷の色々な所の音が聞こえて来るらしい。ラジオが喋る度に、見知った顔がにとりの頭に浮かんで、消えた。それがいささか疲れた。
「こうして聞くと、馬鹿ばっかりだなあ……」
変人ばかりなのは分かり切った事ではあったが、こうして知り合いのプライベートを目の当たりにすると、複雑な気分になった。だが、聞いていた時は悪いような気はしても、思い出してみると瞬く間に笑いが込み上げて来て止まらなくなった。
ひとしきり笑ってから、はたと考えた。最後の守矢神社の声、特に前半の意味不明な演技がかった喋り方は、人に聞かせるためのものであったように思われた。
「そういや、あいつらは『外』から来たんだよなぁ……」
にとりは考えて、翌日守矢神社に赴いた。境内ではやつれた様子の風祝の少女が、箒に寄りかかるような格好で掃除をしていた。
「おーい」
「んぁ……? あ、河童……」
「元気ないね」
「あはは、ちょっとまあ、色々ありまして」
「ふぅん」
にとりは思い出し笑いをこらえながら、何食わぬ顔でラジオを見せた。
「これ、何だか知ってる?」
風祝の少女は一瞬顔をひきつらせたが、努めて冷静な様子で、「ああ、ラジオですね」と言った。
「やっぱ知ってるんだ」
「知ってますよ。でもここじゃ放送なんて入らないでしょう?」
「んー、何というか……ぶふっ」
「えっ何? 何かついてる?」
突然吹き出したにとりに、風祝の少女は驚いて自分の顔を撫で回した。
笑いながらも、何とかラジオの全容を聞き出したにとりは満足した。しかし風祝の少女は訳も分からず笑われているのに不満らしく、段々不機嫌になって頬を膨らました。
「なんですかもう、失礼な」
「ごめんごめん……ともかく、その放送局とやらが出来れば、ラジオに音を飛ばせるんだね?」
「そうですよ。それで外には色々な放送があるんです」
「ふぅん……東風谷早苗のオールナイト・ニッポンとか?」
「うえっ!?」
「くくくくっ、あんたの録音もそのうち日の目を見るといいねえ」
軽口で言ったつもりだったが、風祝の少女は「きぃーっ! 何で知ってるんですか! 口封じ口封じ!」と顔を真っ赤にしてにとりに襲いかかった。
「うわ馬鹿、やめろって!」
「盗み聞きなんて盗み聞きなんて! 常識がないんですか、あなたはっ!」
「ひええ」
危うく退治されかかった所を逃げ出して、にとりは息をついた。風祝の少女は異様に強かった。
「現人神って……ありゃ修羅じゃん」
息を整えて、気が付くとそこは鉄塔であった。相も変わらず黙ったまま、長い影を伸ばしている。
放送局とやらの構想でも練ろうかと、にとりは鉄塔に上って定位置に腰を下ろした。強い風がびょうびょう吹いていた。夏の匂いはもうせず、時折ひやりと首を撫でる辺りなどに冬の気配が潜んでいた。
にとりは、ああでもないこうでもないと頭の中で妄想をこねくり回して、形にしようと試みたけれど、実際に電波を飛ばすのはどうすればいいのか、イマイチ分からない。風祝の少女も、その細かい仕組みまでは分からないらしい。
風が雲を運んで来て、鉄塔も雲の中に入ったので、白い靄がにとりの視界を覆った。日が暮れかけているので、余計に暗かった。だが妖怪であるにとりには何の障害にもならない。水滴で体がじっとりと濡れるのも、河童には心地よかった。
目を閉じて、膝に乗せたラジオを抱くようにして考え込んでいたが、いよいよ埒が明かなくなって来た。第一、河童は机上で空論をいじくるよりも、現場で体を動かす方が性に合っているのだ。
にとりは伸びをして、自分に言い訳した。
「はー……まあ、なんとかなるかな。楽しみは先に取っとけってね」
『――ガンバレヨ――』
にとりは驚いて目を開けた。
確かにスイッチを切っていた筈のラジオから聞こえたその声は、低く、どこかくぐもったような響きを持っていた。
にとりはきょろきょろと辺りを見回した。誰も居ない。喋ったのはラジオか、それとも――、
「……あんた?」
鉄塔はその問いには答えず、相変わらず黙ったまま、にとりをその腕に乗せて突っ立っていた。いつの間にか雲は流れていて、満点の星空が輝いている。
すっかり暗いのに、鉄塔には昼間の残光が微かに残っているようで、にとりの周囲には不思議な薄明かりが満ち満ちている。にとりはラジオのスイッチも入れず、ぼんやりと空を眺めていた。
風がびょうびょうと吹いている。

初めて絵がー、さすがモジカキヤ氏だぜ
今後も挿絵があるといいかな(チラッチラッ
最後の辺りで「キーリ」を思い出しました。
良かったです
鉄塔は昔から好きだったのでこのSSはすごく楽しめました。
挿絵とも合わさって良い雰囲気を味わえました。
鉄塔最近無くなってますよね、地面に埋まってるとかなんとか。
少し寂しいです。
ただ、仕上げるのに手間がっかるので、無理せずゆっくりと続けていってもらいたいです
早苗がラジオごっこやるのって、どうしてこんなにも似合うんでしょうかね?
夜空を見ながらラジオを聴くのはいいですね
情景が伝わってきました
鉄塔は景観に悪影響を及ぼすと批判されることがありますが、
もし鉄塔を全て撤去してしまったら、それはそれで寂しく思う人がそれなりにいると思うんですよ
てろてろの時間が流れていてとても素敵でした