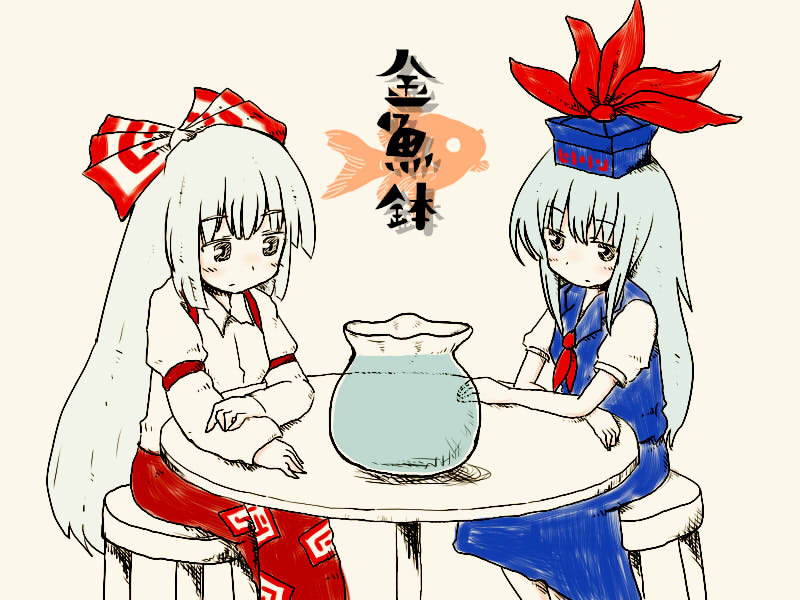
その年の幻想郷は水無月にかかった雨雲が文月の終わりまで出て行かず、梅雨の晴れ間も見せぬまま無暗に雨ばかり降らした。どうも外界が空梅雨で、ちっとも雨が降らなかったのが原因であろうと思われた。
初めのうちはただ辺りがずっと湿気ていて、ジメジメして、嫌な感じだなと思うばかりであったが、常に降り続ける細かな雨の合間に、突如としてざばざばと桶をひっくり返したような雨が断続的に降って、次第に霧の湖の水量は増え、妖怪の山の渓谷に地滑りが起こり、一時期天然のダムと化していたのだが、降り続ける雨によってとうとうダムが決壊し、人里は床下浸水から床上浸水にまで発展し、人々は「うひゃひゃひゃ」と言いながら家財道具を抱えて家の二階や一階の屋根の上に駆け上がった。
そうして文月の終わりになってようやく梅雨雲も何処かへ行ったのだが、
「まさか里が水没するとはなあ……」
上白沢慧音は、寺子屋の屋根の上に仁王立ちしたまま嘆息した。
頭上に居座る空は青く、雲一つ流れてはいない。太陽はぎらぎらと夏の日差しを容赦なく投げ付けている。その日差しを、里の家々の間に溢れている水が照り返していた。
水は民家の一階をすっかり水没させ、二階の窓際の水面が時折ちゃぷちゃぷと波を立てて部屋の中を濡らした。
半人半獣の慧音とて、さすがに自然現象までも食い止められない。水没した歴史を食ってしまおうかとも思ったけれども、それだって万能ではない。
かつて月がおかしかった晩はやむにやまれず能力で里を隠したが、無暗に歴史を食えば、どうしても不自然になるし、何処かでしわ寄せが来る。第一、里の外まで水でひたひたと溢れているのであるから、里だけの歴史を食っても意味があるまい。しかし幻想郷じゅうの歴史を食い尽くすのはさすがに骨が折れる。
それでも、人間が大好きな慧音にとっては、里が水没するという事件は、骨を折っても食うに値すると思われたのだが、慧音の目の前では、里人たちがいつもと変わらぬ様子で生活していた。もちろん、水の中に入るわけにはいかないのだが、歩く代わりに小舟が行き交って、店は二階の部屋や一階の屋根の上に開かれている。少し向こうでは子供らがはしゃぎ声を上げて泳いでいた。
こういう風景を見ると妙に脱力してしまって、下手に歴史なんぞ食わなくてもいいか、と思ってしまうのである。
風景だけではない、実際に慧音は里人たちに協力を申し出た。しかし、里人たちはそれを笑って辞退した。
「なぁに、たかが水に浸っただけでさあ」
「別に人が死んじゃいないですし」
「や、甘木のとこのばあさんは死んだぞ」
「ありゃ寿命でしょ、雨が降ってる最中にくたばったそうじゃないですか」
「百六つの大往生だから、むしろお祝いだったなあ」
「わっはっは」
「しかし、道がぬかるんで、葬式は大儀だったな」
「埋めたばかりで死体が浮かび上がらなきゃいいけど」
「いや、なんか死体は火車にさらわれたらしい」
「ありゃ、あの棺桶は空だったのか」
「骨と皮みたいなばあさんだったから軽いと思ったが、中身がなかったとはな」
「おいおい、甘木のばあさんの話じゃないよ」
「そうだった」
「何の話さ」
「町の修復だろう」
「ま、壊れたものは直せばいいですし」
「慧音先生のお手を煩わせるまでもありませんやね」
どうにも里の人間たちは状況適応力が高い気がしてならぬ慧音であった。
今夜は里の夏祭りが開かれる予定である。里が水没しては、水が引くまで開催は出来ないだろうと思っていた慧音だが、里人たちはそんな事はちっとも思っていないらしい、祭りだ祭りだと大騒ぎしながら、柱を立てて縄を渡して提燈をぶら下げたり、屋台の位置取りの打ち合わせをしたりしている。
「なんか心配するのが阿呆らしくなって来た……」
慧音は妙にくたびれた足取りで、かたかたと音をさして瓦の上を歩き、小舟や木樽をいくつもつなぎ合わせて上に板を渡した所にある、急ごしらえのカフェに降り立った。
慧音が乗るとカフェの床はぎいぎいと揺れたが、ひっくり返る様子はない。あちこちに日傘代わりの大きな番傘が差してあって、その下に椅子とテーブルが置かれて、そこで大勢のお客が談笑している。
ちゃぷちゃぷと揺れる水の音が涼しげだが、陽気は夏のものだから、暑い。
慧音は冷たい紅茶を注文して、水浸しの里を何ともなしに眺めた。家が水没しているのに、何の悲壮感もないまま、人々は生活している。行き交う小舟が不意に居なくなる瞬間があって、その時はしんしんと張りつめた水面が鏡のように空を映した。
カフェの脇には豆腐屋だった建物があって、そこの二階の窓から店主の化け狐が水面をのぞいたり、二階に運び上げた豆腐作りの道具を拭いたりしている。慧音が眺めていると、窓際の水がぷくぷくと泡立ち、水の中からざぶりと何かが出て来た。人魚のわかさぎ姫であった。わかさぎ姫は重なった木の桶を豆腐屋に手渡した。
「はぁい、あったわよー」
「おう、ありがとよ」
「人魚姫さーん、こっちも頼むよー」
「こっちもよろしくねー」
「はいはーい、順番よー」
どうやらわかさぎ姫は、水没した家から取り残した家財道具を運び上げる手伝いをしているらしいのである。わかさぎ姫は、ぼんやりと眺めていた慧音に気付いたらしい、ちらと視線をやると、にっこり微笑んで小さく手を振った。
何やらここのところは人間と妖怪の距離が無暗に近いように感ずる。襲い、退治されるという関係がほとんど形骸化しているのもあるけれど、それにしたってこれでいいのだろうか、と慧音は考える。
妖怪の存在の根源は恐怖である。最も強い恐怖は死に対するものであろう。さすれば、襲われ、食われるかも知れないという恐怖こそが、妖怪を妖怪たらしめているのである。
しかし、それで実際に自分の教え子が妖怪に食われたり、知り合いの妖怪が里の退治屋に倒されたりするのを想像すると、良い気持ちはしない。
「結局、これでいいって事なのかな」
慧音は椅子の背もたれに深く体を沈めて、向こうの青い空を見た。水明かりが辺りでちらちらして、いつも以上に明るい。紅茶に入っていた氷が溶けて、からんと音を立てた。
日が次第に西の方に傾いて、影が長くなっている。日陰に居ても、じわりと額に汗がにじむような陽気である。何処か爽やかさのあった午前中の光と違って、もったりとした、色あせたような光がそこらを照らしていた。
寺子屋も水没してしまっているし、今夜はお祭りだし、手伝いも断られたし、慧音はする事がない。すっかり氷も溶けて、ほとんど水になっている紅茶を騙し騙しすすりながら、動き回る人々をぼんやりと眺めていると、かたりと音がして、隣に誰か腰かけたらしい。
「や」
「妹紅じゃないか」
藤原妹紅は注文を取りに来た店員に何か言って、慧音の方に向き直った。
「らしくないね」
「なにが」
「慧音がそんな風にぼんやりするなんて」
「何にもする事がないんだ。寺子屋は水の中、子供らはお祭りではしゃいでるし」
「たまにはそういう時間も必要よ」
「でもね、突然時間を与えられると、結構困惑しちゃうのよ。忙しいのが普通だったりすると」
「そういうものかしらね」
ぱしゃん、と水しぶきが上がったと思ったら、近くの屋根から子供らが水に飛び込んでいた。濁っていた水はここ数日ですっかり澄み渡り、水際から見れば底まで見通す事が出来て、湖や山から流れて来たのだろう、魚たちが涼しげにすいすいと通り過ぎて行く。
暑い。泳ぎたい。
慧音はそう思ったが、さすがに服のまま飛び込むのは憚られるし、体裁も矜持もある。こらえながらうずうずしていると、店員が麦酒を運んで来て妹紅の前に置いた。
「あ、昼酒、ずるい」
「えへへ、今日はお祭りだし、固い事は言いっこなしだよ」
そう言って、旨そうに麦酒を飲んでいる。そうして、うずうずと体を震わす慧音を見て、いたずら気に笑った。
「飲めばいいじゃない。仕事があるわけでなし」
「むう……」
慧音はもじもじしていたが、この暑気の中、冷たい麦酒の誘惑には勝てなかったらしい、開き直ったように手を上げて、店員に麦酒を運ばした。
日がずんずん沈むにつれて、二人のテーブルにはグラスが幾つも置かれた。昼酒とはかくも旨いものかと慧音は驚いた。
「いけないな、飲み過ぎちゃう」
「そりゃ麦酒だし。他のにする? 冷酒とか……」
「それは日が落ちてからにしようよ。水面に映る提燈の明かりを見ながら飲むの。ふふ、きっと美味しい」
妹紅はぽかんとしていたが、こらえ切れなくなったようにくすくす笑い出した。
「なんだ、しっかり楽しんでるじゃない」
「むっ」
慧音はバツが悪そうに口をへの字に結んだ。
遠くでとんつくとんとん、とお囃子が鳴り出した。辺りはおもむろに騒がしくなって来ていて、低くなった太陽で影が長く伸びている。西の空が焼けて、山の向こうで大火事が起こっているようであった。
「竹林もやっぱり水浸しよ。永遠亭はどうだか知らないけど」
「阿求は大変みたいだよ、前八代分の書き溜めた縁起を家人総出で二階に逃がしたとか」
「大丈夫だったのかな?」
「いくつか駄目だったみたい。水が引いたら、その分の歴史をどうにかして欲しいって頼まれたよ」
「おーい、麦酒もう二つ」
「妹紅の家も片付けが大変だろう? 水が引いたら手伝いに行くよ」
「そりゃ助かるけど、寺子屋の片付けの方が大変でしょ? むしろわたしが手伝いに行くさ」
「お互いさまだな」
「そういう事」
天秤棒の両側に、大きな金魚鉢をぶら下げた金魚売が、とんとんと軽快な足取りで屋根を渡って行く。子供らが面白がって、「金魚だ金魚だ」とその後ろを付いて行く。夕日を照り返す金魚鉢の中で、赤や白の金魚たちがゆらゆらと泳いでいた。
七つ目のグラスを空にしたところで、妹紅が立ち上がった。
「少し歩こうよ」
「うん」
二人は瓦をかたかたいわしながら、夕暮れの街並みを当てもなく歩いた。
次第に焼けていた空が大人しくなって、稜線が橙色、そこから天頂に至るにつれて紫色、藍色と絵具で重ねたように続いている。
星がひとつ輝いた。柔らかな、肌触りの良い風が向かいから頬を撫でる。少し火照った顔には丁度いいように思う。
提燈の明かりが揺れる水面で飛び散らかって、行き交う人々の顔に不思議な陰影を投げかけている。すっかり日が暮れた。
屋根の上や二階、水上の急ごしらえの筏の上で、職種色々の屋台がお客を呼び込んでいる。良い匂いのする煙が流れ、お囃子の音、雑踏、水の音、歌声、楽器の音、そんなものがみんな混じり合って耳に飛び込んで来た。
屋根の上を取れなかったらしい香具師たちが、小舟を屋台代わりにしているらしい、商品を満載して水の上を行き交っている。
「お囃子だ」
妹紅が指さした先に、提燈をいくつもぶら下げた屋形船が流れて来た。上にお囃子連が乗っていて、太鼓や笛の音に合わせてひょっとこやおかめが滑稽な仕草で踊っている。
「なんか妙なのが混ざってるね」
「うん」
成る程、踊っている中に、いくつもお面を浮かべた無表情の少女が混じっている。あれはいつだかに異変を起こした妖怪ではなかったかしらん、と慧音は思った。
妹紅は面白そうな顔をして、流れて行く屋形船を眺めていた。
「楽しそうにやってる」
「うん」
「祭りとはいえ、一昔前はここまで妖怪だらけでもなかったのにね」
「うん」
「……どうしたの、慧音。なんだか元気がないよ」
妹紅が慧音の顔を覗き込んだ。いつの間にか俯いていた自分に気づき、慧音は驚いた。ずっと心の中にあったモヤモヤが、ふつふつと沸いて来るようであった。
「……もうわたしは必要ないのかも知れないな」
「ん?」
「人里を守ろうとなんてしなくていいって事」
そうなのだ。こうやって、水浸しになろうが、妖怪が一緒に舟に乗っていようが、笑って過ごせる人間たちが、自分の助けなど必要なのだろうか?
自分は外敵から里を守る事は出来る。しかし、今人間たちは、その外敵である筈の妖怪たちと上手くやっている。それは自分が手引きしたわけではない。人間たち自身が変わっただけの話だ。
「こんな事、引け目に感じる必要はないのにね」
慧音は自嘲気味に笑った。妹紅は黙っている。屋形船はとうに遠くへ流れて行ってしまった。
「やっぱり、半分人間だからかな、みんなに置いて行かれたみたいに思うんだ。力があるのに、必要とされない。本当に必要なものは、人間たち自身が持っているんだ。今日退屈になってみて、何だかありありと感じたよ」
我ながら、随分下向きな事を言うものだ、と慧音は苦笑した。きっと麦酒を飲み過ぎたせいだろう。
妹紅はしばらく黙っていたが、ついと滑るように慧音に近づくと、やにわにその頭を掴んで引き寄せた。額と額がこつんと当たる。鼻先が触れ合いそうに近い。妹紅は目を閉じていた。
「も、妹紅……?」
「わたしは、大勢の人たちに置いて行かれちゃったよ」
慧音はハッとした。妹紅はすでに長い時間を生きている。
「……ごめん」
「慧音の事を否定してるわけじゃないよ」
妹紅は目を開けて、まっすぐに慧音を見た。自分を覗き込む妹紅の瞳の色の中に、慧音は自分の姿が映っているのを見た。
「半分人間で、強がってるけど弱っちくて」
「ん……」
「わたしたちは、よく似てる」
「……酔ってる?」
「お互いさまでしょ?」
遠い祭りの喧騒が、嫌に大きく聞こえる。どちらともなく笑いが漏れ出して、二人は無邪気にけらけらと笑った。
「似た者同士だ」
「うん」
「人助けにやり甲斐を感じるのも」
「うん」
「心が弱いのも」
「うん、うん」
ぱっと、開放感を感じた。妹紅が手を離して、踊るような足取りで後に下がった。
「一人じゃないさ」
その時、近くで硝子が割れるような音がした。わあと子供らの歓声が上がり、「金魚が! 金魚が逃げた!」と金魚売が騒いでいる。
慧音と妹紅は、水端にしゃがんで覗き込んだ。
水の中で、里の灯を受けてぎらぎらと光る金魚の赤い鱗がありありと見えた。
大きな水害の前だと人間おかしくなっちゃいますね。
もこけーね! もこけーね!
河童の里流れはなかったのかな?
確かな筆力と原作への敬意が感じられます
災いは強引にでも福にしてしまえ、というやつですね
非日常でありながら幻想的な雰囲気が素敵でした
お話、というより、世界のワンシーンを切り取った絵のような印象を受けました。
景色が脳内で鮮明にながれました。
とても雰囲気のよいお話でした。
面白かったです。
これからも応援してます!!